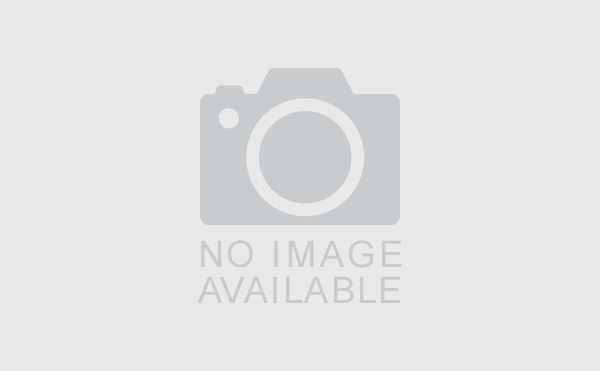飲食店の自社ブランド化とD2C実践~小さく始める冷凍・EC販売~
目次
はじめに
常連さんから「家でも食べたい」と言われることはありませんか。看板メニューを自社ブランド商品にして販売する動きが増えています。店頭の物販やEC販売、冷凍食品化など、やり方はさまざまです。この記事では自店の看板製品を自社ブランド化して、お客様が自宅でも楽しめるよう冷凍食品等の形態で販売する事例や実践例を紹介します。
D2Cとは
D2C(Direct to Consumer)は、自社で企画した商品を自社ブランドとして直接お客さまに届ける考え方です。飲食では、看板メニューを冷凍・常温化して店頭物販・自社EC・自販機・定期購入などで販売し、顧客データと関係性を自店で育てるのが特徴です。中間流通に依存しすぎない点がポイントになります。
ECとの違い
ECは売る手段で、D2Cはブランド作り〜届け方〜関係づくりまで含む設計です。モール販売だけでも始められますが、自社で世界観や体験を統一し、到着後の案内や再購入の導線まで整えると、D2Cとしての効果が高まりやすいです。小さく試し、反応を見て磨いていく流れが現実的です。
期待できる効果と注意点
効果は、来店外の第二の売上柱、24時間の接点拡張、レビュー・購入履歴を使った再購入促進などです。一方で、表示・衛生の遵守、安定製造、在庫と賞味期限、配送コスト、お問い合わせ対応など運用の地力が問われます。最初はSKUを絞り、無理のない体制を組みます。
その際成功のコツは体験の統一が肝心です。開封〜解凍〜盛り付けまでの再現手順を丁寧に設計し、同梱リーフレットで迷いを無くします。店頭ではPOP・声掛け・受け渡し導線を整えます。省人化の工夫は既稿「セルフサービスの進化」の内容が応用できますし、見せ方やツールは「販促ツールの使い方」が参考になります。
向いているケース/向かないケース
向いているのは、味の再現性が高いメニュー(スープ・煮込み・揚げ物など)、ギフト・土産の需要がある店、SNSにファンがいる店です。向かないのは、日持ちが極端に短い/設備制約が大きい/店舗提供が複雑で家庭再現が難しい場合です。迷う時は小ロットの季節セットから検証します。
最近の動き・背景
テイクアウトや物販は、来店頻度が下がる時期でも売上の“もう一本の柱”になりやすいです。ラーメン分野では、名店の味を冷凍で届ける宅麺.comが**加盟700店超・取扱約1,800種・会員55万人(2025年5月時点)と公表し、モール外でも販路を広げています(出典:「宅麺」が創業初、ロゴとパッケージデザインを刷新 | グルメエックス株式会社のプレスリリース)。
独自ECで小さく始める個店も目立ちます。国内サービスBASEは食品カテゴリの事例を多数公開し、スイーツや惣菜など少量・限定販売→レビュー改善で立ち上げる流れが見えます(出典:BASEのフードショップ事例紹介 - 無料で簡単なネットショップ作成サービス BASE)。まずはセット商品で反応を見る始め方が現実的です。なお、店内掲示やPOPの工夫は、既稿「販促ツールの使い方」の考え方がそのまま活かせますのでご参考下さい。
店外チャネルでは**冷凍自販機「ど冷えもん」が拡大し、**設置8,000台超(2023年8月時点)が広報取材で示されています(出典:コロナ前から冷凍食品自動販売機を考案、2年間で8000台販売した「ど冷えもん」広報部にあれこれ聞いてみた - メシ通 | ホットペッパーグルメ)。24時間・非対面での販売ができ、人流や時間帯に応じてSKUを調整しやすいのが利点です。
導入時の課題
最初の壁は製造体制です。既存厨房での仕込み拡張か、外部の製造委託(OEM)の選択になりますが、店内で作るならピークを避けた仕込み枠と衛生導線の見直しが必要です。OEM活用ならレシピ再現性、最小ロット、納期、歩留まりが協議事項となりますが、いずれも最初は小ロットで需要を確かめるのが安全といえるでしょう。在庫と賞味期限の管理についても、店内オペレーションへの影響が出やすい部分です。週次の仕込み上限を決め、販売データを見ながら調整します。
表示と衛生についても導入時に気を付けるべきポイントです。ラベルには品名、原材料、アレルゲン、内容量、保存方法、賞味期限、解凍・加熱方法、製造者情報を分かりやすく記載します。基礎は消費者庁の資料を確認し、疑問は早めに保健所へ相談すると安心です(参考:別添 食品期限表示の設定のためのガイドライン)
販売の際の課題はいかに来店客にセット売りを促進するかです。価格は原価ベース(製造原価+人件+梱包資材+配送費)で設計しつつ、店舗受け取り割やまとめ買いセットで送料の心理的ハードルを下げます。また、店頭導線づくりも効果的です。レジ横や受け取り口にミニ冷凍庫や棚を置き、POPで「今の味をご自宅でも」と伝えます。スタッフが自然に案内できる一言トークを用意すると提案が安定します。POPの作り方やツール選びは「販促ツールの使い方」の要点が参考になります。
取り組み事例やヒント
例1:看板メニューの冷凍化 → プラットフォーム販売
既存の冷凍販売プラットフォームサイトが世の中でも認知度が高いラーメン系は検証がしやすいカテゴリです。まずは宅麺.comのような既存プラットフォームで需要と価格帯をテストし、レビューで指摘された“麺のコシ”や“スープ量”を微調整。手応えが出たら、店頭物販・自社EC・自販機へ横展開します。
例2:ECモール+自社サイト併用(小さく開始)
そうしたプラットフォームが存在しない場合はECモール+自社サイト/SNS併用でのスモールスタートを検討します。独自ECは数量限定セットで立ち上げ、レビュー収集→写真・説明の改善→セット見直しによりPDCAを回します。店頭POPとSNSでの入口も用意し、店舗受け取り割で送料障壁を下げることがポイントです。。食品系のページ作りや運用は、BASEの公開事例が参考になります。店内導線とPOP配置は「販促ツールの使い方」の基本に沿うと迷いにくいです。
例3:地元コラボ商品(季節・地域性の付与)
需要を喚起する方法として地域食材とのコラボは物語性と期間限定性で手に取りやすくなります。少量ロットの冷凍OEMを併用しつつ、まずは季節セットでテストし、売れ筋だけ定番化します。
例4:自販機チャネルのテスト導入
店外チャネルでは**冷凍自販機「ど冷えもん」を自店前に設置することも考えられます。自販機チャネルは導入/ランニング費用は発生するものの、接客が不要、店舗営業時間外でも購買が見込めることが利点です。自販機チャネルでは、有名店の冷凍ラーメンを扱うヌードルツアーズのような形で“比較購買”を促す棚割も手です(参考:ヌードルツアーズ 公式サイト)。
おわりに
いかがだったでしょうか。自社ブランド化やD2Cは、いきなり大掛かりにしなくても始められます。店頭の“ついで買い”で手応えを確認し、ECや自販機で二本目・三本目の導線を足していく設計で始めれば導入の障壁を軽減できます。まずは看板メニューの小ロット冷凍から、店内POPとスタッフの一言トークを用意してテスト販売を始めてみませんか。
当研究会には飲食店経営診断の知見を有するメンバーが多数在籍しており、補助金申請に向けた相談を受けることも可能です。是非お問い合わせページよりご相談をお待ちしております。
当研究会では中小企業診断士資格を持つ様々なメンバーが、飲食店の診断実務ができる人材の育成と組織体制の構築を目的として、会員の経営診断技術の研鑽や、研究会の診断ノウハウの蓄積を行っております。
具体的には、研究会(月1回)の飲食業界に関する調査研究や、オープンセミナーの開催、プロジェクトチームでの飲食店支援実務など、幅広く活動しております。