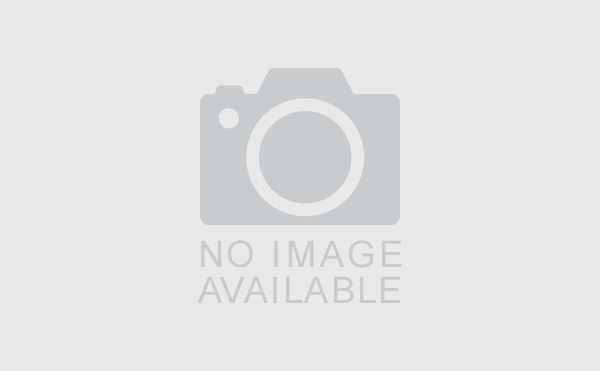20250304セミナー参加報告 「飲食店経営と障がい者就労支援 」

近年、障がい者の社会参加を促進する取り組みが注目を集めています。 その中でも、飲食業と障がい者支援を融合させた事業は、地域社会に新たな価値を提供する重要な役割を果たしています。 今回のセミナーでは、中小企業診断士でもある宮川公一さんが手掛ける障がい者就労支援事業を通じて、飲食業がどのように障がい者支援に貢献しているのかお話しいただきました。
障がい者就労支援事業は、一般就労が難しい障がい者や高齢者、生活困窮者などに働く機会を提供し、職業スキルを身につける支援を行うものです。 宮川さんは、障がい者支援を通じて「働く人が幸せ、お客様が幸せ、社会が幸せ」という理念を掲げ、地域社会に貢献する活動を展開しています。
就労支援にはいくつかの形態があります。例えば、「就労移行支援」は一般企業への就職を目指す障がい者に職業訓練や就職活動のサポートを提供します。一方、「就労継続支援」にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)があり、障がい者の特性に応じた働き方を選べる仕組みが整っています。
宮川さんが運営する就労支援事業所では、飲食業を通じて障がい者が社会参加できる場を提供しています。東京都渋谷区の「渋谷まる福」(A型事業所)では、障がい者が手作りパンや焼き菓子を製造・販売し、接客や製造技術を学びながら働いています。また、渋谷区役所内1階で営業する「渋谷ハチ公そば」(B型事業所)では、蕎麦職人が支援利用者とともに十割蕎麦や天ぷらを提供し、素材にこだわった絶品メニューをリーズナブルな価格で提供しています。
これらの事業所は、単なる作業所ではなく、一般に通用する質の高い商品を提供することで、障がい者が社会の一員として認知される場を作り出しています。実際に、「渋谷まる福」のパンや焼き菓子はホテルに納入していたり、渋谷区の敬老の日ギフトに採用されたりしています。「渋谷ハチ公そば」は、11時から14時半までの営業ですが、最高で150食を販売するなど多くのお客様に利用されています。
支援利用者も、「焼き菓子をうまく焼けるようになりたい」、「接客をうまくなりたい」、「体力をつけて一般就労をしたい」など、目標に向かって努力し達成する喜び感じています。
また、宮城県亘理町では、東日本大震災の被災地支援からスタートした事業所「いちごいちえ」(B型事業所)を運営しています。ここでは、大判焼きの製造・販売や被災農家が作った野菜の販売を行い、地域の復興に貢献しています。障がい者支援と被災地支援を融合させたこの取り組みは、地域社会にとって欠かせない存在となっています。
宮川さんは、「施設外就労」という新たな形態にも挑戦しています。「施設外就労」とは、就労支援事業所の利用者が職員とともに企業内で業務を行う仕組みです。2025年には、自衛隊中央病院内食堂の運営を開始する予定で、ラーメンや定食を提供することで、障がい者が働く場をさらに広げる計画です。この取り組みは、障がい者が地域社会の中で活躍する場を増やすだけでなく、飲食業の新たな可能性を示しています。
障がい者支援事業には多くのやりがいがありますが、同時に課題も存在します。サービス管理責任者などの専門職採用、職人と利用者のコミュニケーションや収益モデルの構築など、事業運営には多くの工夫が必要です。しかし、宮川さんは「多様性の受け入れ」(Diversity)、「地域社会への貢献そして外へ」(Glocal)、「社員、利用者の幸せの創造」(Wellbeing)、「一人一人の創造性への挑戦」(Creativity)、「不用品、廃棄品の利活用」(Environment)、「身体によい食材を」(Good food for Health)、「新しい文化の創出」(New Culture)などを掲げ、未来に向けた挑戦を続けています。
飲食業と障がい者支援の融合は、地域社会に新たな価値を提供するだけでなく、障がい者が社会の一員として活躍する場を広げる重要な取り組みです。宮川さんの活動は、障がい者支援の可能性を広げるとともに、地域社会の発展に寄与しています。これからも、飲食業を通じた障がい者支援が多くの人々に幸せを届けていくことと思います。